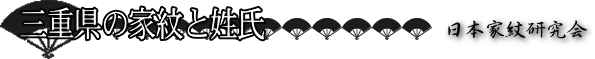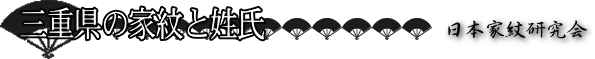三重県の旧国名は伊賀、伊勢、志摩の三国と紀伊国の一部である。
伊勢湾、熊野灘に面し南北に細長く、翼を広げた大鷲の姿に似ているといわれる。
[三重]という語源はむかし日本武尊が能褒野(のばの、亀山市)で病いに倒れたとき、「その足三重の勾玉の如し」と[古事記]に載っていることよりといわれる。
また古くから伊勢神宮の所在地として全国に知られる。このため姓氏もこの伊勢神宮に関連のある、荒木田姓、度会姓、中臣姓が多く見られ、家紋においても関連する柏紋、桐紋が多い。また伊勢平氏発祥の地であり蝶紋も比較的多く見られる。特に注目されるのは片喰紋が全県的に圧倒的に多く用いられていることである。
四日市を中心とする県北部は一大工業地帯となり、人口の移動も多く、姓氏、家紋も従来から大きく変化している。 |
|
三重県の家紋調査姓氏数
総数 13,097姓氏 |
| 調査姓氏数 |
| 三重県北部地方〔四日市市、桑名市、鈴鹿市他〕 |
3,778姓氏 |
三重県中部地方〔津市、亀山市、上野市、久居市、名張市、
松坂市他〕 |
6,113姓氏 |
| 三重県南部地方〔伊勢市、鳥羽市、熊野市、尾鷲市他〕 |
3,206姓氏 |
| 三重県全県 |
13,097姓氏 |
|
|
|
|
|
|
|